このブログでは Harry Potter を英語で読んでみたいという方々へ向け、様々なアドバイスや読み進める際のポイントを解説しています。
今回は、 Harry Potter and the Deathly Hallows (ハリー・ポッターと死の秘宝)で登場する重要な固有名詞について、その意味や名前の由来などを解説します。
※映画のPART1の内容までを解説します。
Harry Potterの作者の J. K. Rowling は、ラテン語や英語の要素を組み合わせて、面白い固有名詞を作り出すことで有名です。原書や映画を見る前に、作者の J. K. Rowling が言葉に込めた意味を知っておくとより楽しめること間違いなしです!
このページでは、次の内容を解説します。
- 灯消しライターの英語名は?
- カッコ良すぎる名前、ゼノフィリウス・ラブグッド
- 吟遊詩人ビードルと韻を踏んだ仲間たち
- R. A. B.の正体と名前の由来
ぜひ最後までご覧ください!🧙

さっそく見ていこう!
金曜ロードショーを見逃した人にはAmazonプライムビデオがおすすめ!↓

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 (字幕版)
死の秘宝 PART1 固有名詞の語源解説
この記事では「ハリーポッターと死の秘宝 PART1(Harry Potter and the Deathly Hallows)」に登場する言葉について、英語名の語源を紹介します。
灯消しライター(Put-Outer, Deluminator)
灯消しライターはダンブルドアが所持していた魔法の道具で、遠くにある街灯の灯りを消したり再び点けたりすることができます。
シリーズでの初出は1巻「賢者の石」の1章です。
ダンブルドアがダーズリー家にハリーを預ける際、周辺の家から見られないように Privet Drive(プリベット通り)の全ての灯りを消すために使われていました。
その後は登場せず、7巻「死の秘宝」で久々の登場となります。ではダンブルドアの遺品としてなぜかロンに引き継がれ、その隠された力で重要な役割を果たします。
英語での表記は Put-Outer または Deluminator です。
Put-Outer
1巻1章では Put-Outer と表記されていました。
put out は「(火や明かりを)消す」という意味です。put out に「〜するもの」という意味の -er をつけて、まさに機能をそのまま表現した名前です。
物語の最初に出てくる魔法の道具なので、J. K. Rowlingも機能がわかりやすい名前にしたのかもしれません。
Deluminator
7巻の死の秘宝では Deluminator という名前で再登場しました。
- De-: 「取り除く」という接頭辞。
- Luminator: ラテン語 lumen(光)由来の単語「光を発するもの」。
- Deluminator 全体で「光を取り除く道具」という意味になります。
遺品の受け取りの際には Deluminatorが使われていたので、Deluminator が魔法界での正式名称で、Put-Outer は通称なのかもしれません😄

賢者の石の映画は、ダンブルドアが Put-Outer を使うシーンから始まったね
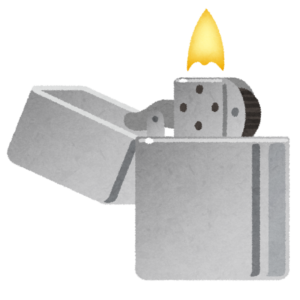
Xenophilius Lovegood(ゼノフィリウス・ラブグッド)
Xenophilius Lovegood(ゼノフィリウス・ラブグッド) は、Luna Lovegood(ルーナ・ラブグッド)の父親として登場します。雑誌『The Quibbler(ザ・クィブラー)』の編集長で、「死の秘宝」のシンボルについて、ハリーたちに重要な情報を渡してくれます。

名前がかっこよすぎる・・・!
Xenophilius はギリシャ語を組み合わせて作られた名前です。
- Xeno: 「異なる」「外国の」を意味する xeno から
- Philius: 「愛する者」「好む者」を意味する philia から
- Xenophilius で「変わったものを愛する者」という意味になります。
Lovegood という姓はかなり変わった名前に聞こえますが、実際イギリスに存在している姓とのことです。
Beedle the Bard(吟遊詩人ビードル)
死の秘宝の謎を解く鍵として、『The Tales of Beedle the Bard(吟遊詩人ビードルの物語)』という魔法界の童話集が登場します。その中でも『The Tale of the Three Brothers』は死の秘宝について詳しく書かれた童謡でした。
Beedle(ビードル)について、明確な意味はありません。
音韻的に「Beadle(教会や学校での案内係、使者)」に似ています。「Beadle」は、スコットランドの教会の伝統的な役割を持つ人を指しています。古風で詩的な雰囲気を持つ名前として音が似た「Beedle」が選ばれたのかもしれません。古い時代を連想させ、童話や詩の伝承者としての役割にあっています。
Bard(吟遊詩人)ケルト語由来の単語で、もともと詩や歌で物語を語り継ぐ人を指します。現代では「詩人」「歌い手」としても使われます。

Beedle the Bard はどちらも「B」で始まっており、日本訳「吟遊詩人ビードル」にはないリズムの良さを感じるのではないでしょうか。
同じように韻を踏んだ名前はハリーポッターシリーズの中でたくさん登場します。少し紹介してみましょう。
- Bathilda Bagshot:バチルダ・バグショット
「魔法史」の著者。ゴドリックの谷に在住。 - Moaning Myrtle:モーニング・マートル(嘆きのマートル)
ホグワーツの女子トイレに取り憑いたゴースト。 - Salazar Slytherin(サラザール・スリザリン)
- Helga Hufflepuff(ヘルガ・ハッフルパフ)
- Rowena Ravenclaw(ロウェナ・レイブンクロー)
- Godric Gryffindor(ゴドリック・グリフィンドール)

Hogwarts の創始者はみんな語呂が良い!😄
R. A. B. の正体と由来 ※ネタバレ注意!
6巻ハリー・ポッターと謎のプリンス(Harry Potter and the Half-Blood Prince)の最後で突如登場した「R. A. B.」、ヴォルデモートの秘宝を盗んだ謎の人物として名前だけ登場していました。7巻「死の秘宝」ではその正体が明かされます。
以下ネタバレ注意!

R. A. B. の正体とその名前の由来を解説するよ
R. A. B. の正体は Regulus Arcturus Black(レギュラス・アークタルス・ブラック)、シリウスの実の弟でした。ホグワーツではスリザリンに所属し、死喰い人にもなります。しかし、ヴォルデモートの行動に反発して死喰い人から脱退、ヴォルデモートの Horcrux(分霊箱)を破壊しようとするのでした。
Regulus
Regulus は星の名前から命名されています。
Regulus(レグルス) は獅子座を構成する星の中で最も明るい恒星、しし座α星です。1等星の一つですが、1等星の中では最も暗い星です。
また、Regulusはもともとギリシャ語で、「(小さな)王」という意味があります。
Arcturus
Arcturusも星の名前から命名されています。
Arcturus(アークトゥルス)はうしかい座を構成する星の中で最も明るい恒星、うしかい座α星です。1等星の一つで、シリウス、カノープスに次いで3番目に明るい恒星です。ギリシャ語で「熊の番人」という意味があるそうです。

獅子座、小さな王、一番暗い1等星・・・
なんだか深い意味がありそうな命名だね
ちなみに、兄の Sirius は一番明るい一等星の名前(大犬座α星)です。ヴォルデモートと敵対した後に再開できていれば、ハリー・ポッターの物語も大きく変わっていたかもしれません・・・。

サブストーリーが見てみたいキャラクターNo.1だね

まとめ
今回は「死の秘宝」に登場する、次の4つの固有名詞について解説しました。
- 灯消しライター(Put-Outer, Deluminator)
→灯りを消すという意味そのまんま - Xenophilius Lovegood(ゼノフィリウス・ラブグッド)
→ギリシャ語で「変わったものを愛する者」 - Beedle the Bard(吟遊詩人ビードル)
→Beadle:スコットランドの教会の使者から - R. A. B.
→獅子座の一番暗い1等星から
作者のJ. K. Rowling は名前付けに非常にこだわっています。このブログではこれからもハリー・ポッターシリーズに登場する固有名詞について紹介していきます。
英語の原書を読むための情報もどんどん出していくので、ぜひほかの記事も読んでみてください。

それではまた次の記事で!🐸
↓↓Harry Potter を英語で読み進めるために、おすすめの本がこちら↓↓

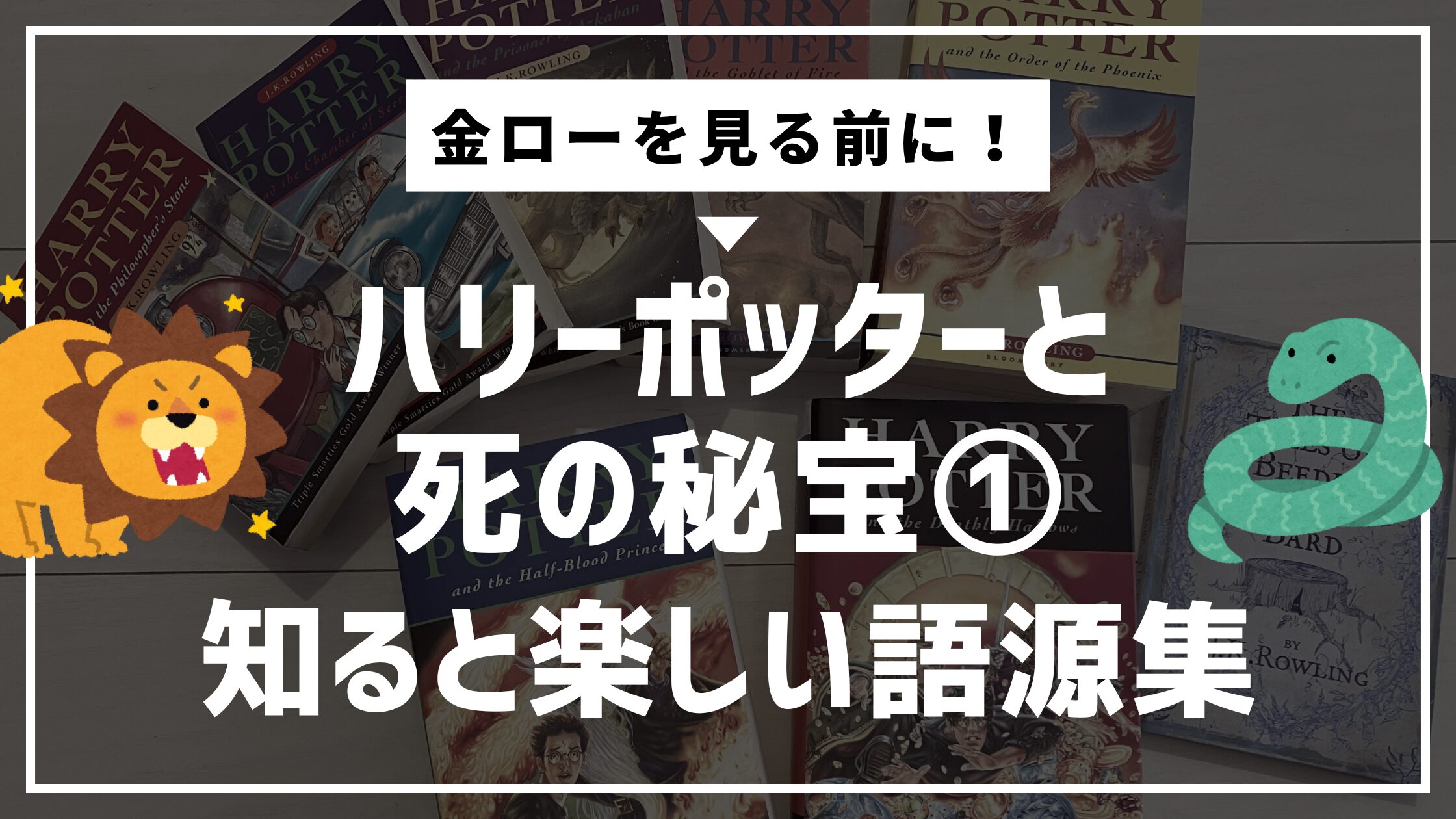
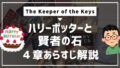
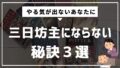
コメント